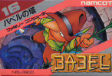_△ ̄▼_△ ̄▼_△ ̄▼_△ ̄▼_△ ̄▼_△ ̄▼_△ ̄▼
今回は【乙女から見る21世紀のコンシュマー産業の行方Vol.86 遊びの進化の足音が聞こえる 前編】からの続きを掲載いたします。
それでは、本文の方を御覧下さい。
_△ ̄▼_△ ̄▼_△ ̄▼_△ ̄▼_△ ̄▼_△ ̄▼_△ ̄▼
スーパーファミコンとプレイステーション。一方がブームとまでは行かず、一方はブームと呼べる段階まで進んだのは、そのハードスペックが新しい遊びを創造する上で大きな助けになるほどのスペックが在ったか否かの差だと思うのです。
スーパーファミコン時代の後期にポリゴン描画という新しいグラフィック処理が家庭用ゲーム機の世界に降りてきました。しかしながら、スーパーファミコン時代では、それらをソフトウェア側で多くを処理していましたので、表現の限界の壁にすぐにぶつかりました。けれど、プレイステーションやセガサターンの時代では、それらの処理はハードウェアで処理することが可能となり、それを利用することでリアルタイムにレンダリングされる3Dの世界をゲームの世界に投入することが可能となりました。
2Dから、3Dへとハードウェアの進化が、ゲームの進化を促したのです。そしてその進化はファミコン時代には無かった遊びを幾つも生み出し、結果、多くのユーザーにビデオゲームの面白さの拡張を認識してもらえるに至ったわけです。
この変革期においては、ハードのスペックは遊びの可能性を広げたという意味で、スペックアップという結果には大きな意義も意味もありました。ですが、ファミコンからスーパーファミコンへと推移していった際に生じた、遊びの進化には繋がらないハードのスペックアップという不毛な並行運動は、プレイステーション以降にも繰り返されてしまいます。
ハッキリ言えば、現時点もその並行運動の惰性の中に居ると言っても、それほど暴論ではないでしょう。
このプレイステーション以降の並行運動こそが、先に記述した"ビデオゲームのハードウェアコンソールの発展というものは、ある時期を境にして、進歩という見せ掛けの殻で覆われた横ばいの進行という形が長らく続いてきました。"っという言い分に繋がるのです。
プレステ以降のハードの世代交代で行われてきたのは、プレステを1つの根幹として、そのプレステに含まれてるテクノロジーをそれぞれ豪華にしてきただけであり、それがプレステ時代では存在しなかった遊びの進化を生むという結果にはならなかったのです。
正に、スーパーファミコンと同様です。
このプレステ以降の時代においては、ネットワークゲームというジャンルが生まれ、それが新しい遊びだと主張する人も居ますが、私は全くそうは思いません。ネットワークゲームの中に"新しい遊び"だと言えるものはどれほどあるのでしょう?
ビデオゲームをネットワークで繋いだことで生まれた新しい遊びと言われる物の殆どが、単にネットワーク回線を媒介してマルチゲームを遊んでるだけにしか過ぎません。どこの誰だか判らない人と一緒に遊ぶという楽しさというのは、確かに新鮮なものでしたが、それはゲームとして新しい遊びに発展したのでなく、マルチプレイの仕組みと過程が変化しただけにすぎず、純粋にゲームとして進化してるのかと問えば、殆どのネットゲームは進化などしていないと言わざる負えないというのが実情でしょう。
好意的に言い換えると、コミニュケーションという要素を組み込むことで、既存のゲームに新鮮な味わいを生み出した事は一定の評価と功績が認められると思ってはいます。斯く言う私もオンラインゲームは嫌いではありませんから。
ですが、やはり遊びの進化という観点においては、ローカルマルチプレイがネットワークマルチプレイに、"レス"ビデオゲームが、"マス"ビデオゲームに成ったに過ぎず、それは進化というより、豪華路線の範囲内とでも言うか、マリオカートがスーパーマリオカートになった程度のことなのではないかと考えています。
よって、ここではオンラインゲームというものが、ビデオゲームという遊びの進化の過程、そしてその平行運動の中で生まれた副産物程度のものであると乱暴に定義します。無論、異論が多くあることは承知していますが、あくまで私個人はそう定義付けます。
そうなると、ゲームはファミコンで生じた第一期ビデオゲームブームの2D時代から、プレステで生じた第二期ビデオゲームブームの3D時代以降、遊びという意味においては進化していないことになります。
この理由に関して、私は常々"平面"という足枷がその進化を妨げてる一番のネックだと語ってきました。
過去に何度も書きましたが、将来のゲーム機というのは、網膜センサーと荷重感知センサーを搭載したヘッドマウントディスプレイを基本のデバイスとして、精度の高いヴァーチャルリアリティーシステムをベースとした姿に成るべきであると事有る毎に書いてきました。
従来のゲーム機は、"ビデオゲーム"と呼ばれてるだけに(日本ではTVゲームと呼称するのが一般的ですが)、モニターというデバイスに接続する外部ストレージにしか過ぎません。
モニターにゲーム機を接続し、ゲーム機で再生されたゲーム映像をプレイヤーがモニターを見て、デバイスで操作するというスタイルが今に至るまでの標準的なスタイルです。しかし、このスタイルがゲームの、そして遊びの進化の大きな足枷になっていると思えて仕方ないのです。
どれほど美麗なグラフィックで緻密に書き込まれた世界が展開してようと、どれだけ完璧にレンダリングされた3D空間が作られていても、所詮はモニターの向こう側だけの世界であり、それは"平面"というモニターを通してでしか、プレイヤーは介入できません。
そんな位置関係に縛られていては、リアルもアンリアルも在ったものではないでしょう。
私の部屋のモニターの横には小さな鉢植えが3つあり、上にはホワイトボードとコルクボードが壁に据え付けられています。
近未来ファンタジーであろうが、現代の戦場であろうが、それがどれほどリアルに描き込まれていたとしても、私の視界には花を付けてる鉢植えや、ファックスで送られてきた仕事関係の書類の切り抜きが貼られたコルクボードに、何度も変更が加えられ、所々に消しきれてない文字の名残が正規の文字に混じったりして、あまり見栄えの良くない、向こう二週間のスケジュールが書き込まれたホワイトボードが見えてるのです。
こんな状況の中で、3Dだ、TPSだ、FPSだっと言われても、極論を言ってしまえば、どれも平面のモニターに映し出される紙芝居にしか過ぎません。
この関係位置から脱却しないかぎり、3Dの先へとゲームの遊びが進化することなど無いと、10年以上前から私は強く思ってきました。
そして、その考えは正しいはずだ…とも思っていました。
_△ ̄▼_△ ̄▼_△ ̄▼_△ ̄▼_△ ̄▼_△ ̄▼_△ ̄▼
この続きの後半は明日にアップ…しない可能性が高いです。恐らく明日は日本対オランダ戦についてのテキストをアップすることになると思います。
逆に日本対オランダ戦を明後日に伸ばして"後編"を明日にアップするかもしれませんが…。
なんかすいません。分割アップにしといて、途中で別の話題を挟みます宣言なんかしちゃって^^;
とりあえず、明日は未定ということで…。
_△ ̄▼_△ ̄▼_△ ̄▼_△ ̄▼_△ ̄▼_△ ̄▼_△ ̄▼
*原文投稿時間不明の為、00時00分として転機しました。